煙に包まれた廊下で“本気の備え”を知った瞬間
こんにちは、3児ママナースのあめです😊
院内防災訓練で、煙が充満する廊下を移動しながら、患者役の叫び声やスタッフ同士の連携にヒヤリとしたあの日。
“想像”だけで知る防災と、“体で覚える備え”には大きな差があると痛感しました。
その後わかったのは、
「訓練で身についたリアルな行動力」が家庭でも職場でも心の拠り所になるということ。
この記事では、
- 訓練参加による学びとは?
- ママナース目線でのリアルな活用法
- 最新技術(VR・オンライン訓練)の活かし方
を、3児ママナース視点で丁寧にまとめます。
✅見出し①|看護師に“訓練が必須”な3つの根拠
①知識・スキル・態度、すべてがアップする効果あり
- 米国看護師協会(ANA)含む研究で、防災訓練に参加した看護師は、知識・スキル・対応力がすべて向上したと報告されています 。
- 特に災害シミュレーションや机上演習を通じて、行動に移す力=態度が強化されるという結果も出ています 。
②定期的に体を使うことで“当事者意識”が芽生える
- サウジアラビアの研究では、「定期訓練を受けた看護師ほど、知識・技能・自信が飛躍的にアップ」したとの結果が確認されています 。
- 訓練は定期的にこそ意味があり、“自己効力感”の違いが実際の労働現場ですぐに現れます。
③“盲点の洗い出し”こそ、訓練の本質
- 現場を模した訓練は、机上マニュアルでは気づけない現場のズレ=盲点を浮き彫りにします 。
- それがあってこそ、 リアルな改善提案→職場にも家庭にも活かせる備えにつながります。
仮想と実際のずれを見つけることが訓練の本質です。
VRやシミュレーションを使う訓練では、本番環境の盲点を発見し修正できるという研究も多数報告されています。
✅見出し②|⏱️訓練当日の“リアルな流れ”を時系列で再現!
「訓練って実際どんなことをするの?」とよく聞かれますが、
私が参加した院内訓練の一連の流れは以下のようなものでした。
🔔9:00|地震発生シナリオにて開始
- 放送で「震度6強の地震発生」と告知
- 看護師・医師・スタッフがナースステーションに集合
- エリアごとに担当が割り振られ、患者対応の指示が出る
👉ここで**「指示待ちではなく自分で動けるか」が問われる**のがポイントです。
🚪9:05〜|患者役の安否確認・搬送開始
- ベッドにいる患者(役)を安全な場所へ移動
- けが人(役)への応急対応訓練
- 非常持出バッグを持ち、避難経路の確認
👉私は担当病棟のストレッチャー誘導を担当しましたが、
エレベーターが使えない設定だったので、階段搬送に。
体力より「チームで声を掛け合いながら移動する意識」の大切さを実感。
🔁9:30〜|訓練後のフィードバックタイム
- グループごとに振り返りシートを記入
- 「うまくいった点/改善したい点」を共有
- 災害委員からの講評とアドバイス
👉この時間が一番学びが多く、
「普段のルーチンがいざという時“制約”になることもある」と気づかされました。
この流れを実際に経験すると、
マニュアルの文章では見落としていた“動線・連携・物品配置”の問題がはっきり見えてきます。
また、家族との連絡手段や、勤務中の子どもの迎えについても、訓練後すぐに見直しました。
🎒見出し③|訓練未経験でも安心!ママナースの“持ち物&心構えリスト”
「訓練って初めてだと何を持っていけばいいの?」という方のために、
実際に私が参加して感じた「最低限これがあれば安心!」というアイテム&心構えを紹介します。
✅持ち物リスト|リュックに入れておけば即対応!
| 種類 | 持ち物例 | 理由・ポイント |
|---|---|---|
| 基本持ち物 | 上履き、筆記用具、メモ帳、スマホ、充電バッテリー | スムーズな移動と連絡の確保に必須 |
| 非常用グッズ | ミニライト、マスク、手袋、携帯用アルコール | 換気や衛生対策として活躍 |
| 女性ならでは | 生理用品、常備薬、ヘアゴム | 緊急時も安心して動けるよう、自分の安心材料を確保 |
| 子育てママ用 | 小型おやつ、子どもとの緊急連絡メモ、写真付き家族情報カード | 家族とすぐ連携できるよう、情報を1枚にまとめておく |
📌特に「上履き」や「スマホ用バッテリー」は現場でもよく忘れられるアイテムなので、あらかじめリュックに常備しておくのがオススメです。
💡心構えリスト|“ただ参加する”だけじゃもったいない!
| 行動 | 理由 |
|---|---|
| 開始前に“想定シナリオ”を聞く | どう動くかのイメトレで焦りが減る |
| 他職種スタッフに積極的に声をかける | 連携ポイントの再確認ができて、安心感が生まれる |
| 終了後に必ず“振り返りメモ”を書く | 学びを言語化し、職場・家庭へのフィードバックに活かせる |
| 家族と「訓練で得た知見」を共有する | 災害時の役割分担や連絡ルートを再確認できる |
特に最後のポイント、「家族と話す」はすごく大事!
ママナースとして、家庭内の避難リーダーにもなれるよう意識しておくと、
実際の災害時にも慌てずに済みます。
見出し④|今どきの防災訓練はここまで進化!注目の最新トレンド3選
昔ながらの避難訓練だけではありません!
最近は、看護師の忙しい勤務事情や家庭との両立を踏まえた、柔軟でリアルな訓練のかたちが増えています。
🥽1|VR訓練:リアルすぎて怖いほどの体験ができる
- 火災現場、暗所避難、煙充満のシナリオをVRゴーグルで360°体験。
- 東京都内の病院や大学病院の災害訓練にも導入され始めており、
「焦り」「視界不良」「足場の不安」など五感で体感できるのが特徴。
📌参加者の声:「目の前で火が見えると、頭じゃなく体で“逃げなきゃ”と動ける感覚になった」
💻2|オンライン訓練:全国どこでも“シミュレーション”できる時代へ
- 災害委員会や院内研修がZoomやLMS(eラーニング)で受講可能に。
- シナリオを用いたケーススタディ、避難計画のチェックリスト記入など、
勤務外でも参加しやすく、ママナースにも好評。
📌「子ども寝かしつけたあとに受けられて助かった」「夜勤の合間にスマホで見られるのがいい」という声も。
🏘️3|地域合同訓練:家庭・職場の両視点が同時に身につく
- 病院だけでなく、地域の保育園・学校・自治体と合同で行うケースが増加。
- 実施例:長野県や兵庫県などでは、看護師・保育士・消防・PTAが連携する防災フェス型の訓練を開催。
📌「職場の知識をそのまま家庭にも活かせた」「避難所での役割がリアルに想像できた」との声が多数。
🌟どれも共通するのは、「ただの避難練習」で終わらせない、“思考する訓練”へのシフトです。
私たち看護師も、日々のスキマ時間でこうした新しい訓練に触れておくだけで、緊急時の自信がまるで違ってきます!
✅見出し⑤|ママナース視点!訓練から得た“リアルに効く5つのレッスン”
1️⃣「音・匂い・混乱」の現場感がやる気につながる
- 訓練で実際にヘルメットやライトを装着すると、
“手が動く”=心が動き、思考が整理された瞬間があります。 - 私も初回で、ペンと紙を取り出す代わりに、
機器を持って動く自分を認識できた瞬間が忘れられません。
ライトをつけ、ヘルメットをかぶると、一気に“行動を意識する自分”になれる瞬間があります。
これは知識だけでなく、身体が反応を覚える心理的効果です。
2️⃣看護師同士の声掛けで、混乱がチームに変わる
- 「〇〇さんはどこ?」「ここは私がやる!」
こうした声かけがチーム内の連携を生み、被災者の安全を守る力になります。 - 研究でも、コミュニケーションの質=災害対応の質と深く関係があることが分かっています 。
訓練中の「こちらに来て!」「□□さんは?」といった声掛けが、医療安全のカギとなることも。
研究でも、コミュニケーション品質=災害対応品質という関係性が明らかにされています。
3️⃣避難エリア&経路の“5分動画レクチャー”が効果絶大
- 「時間を共有する訓練」では、5分後にどこに誰が集合するかを決めることで、
現場の混乱や想定外対応が劇的に減ると報告されています 。
「5分経ったらここに集まる」などの短時間訓練ルールは、混乱を最小化できるとされています。
4️⃣家庭との“緊急連絡フロー共有”が安心感を育てる
- 訓練後、家族に「こうしたら安心」と話すことで、
訓練が家族の話題になり、私自身の不安が減りました。 - 実は、SNSと電話での連絡ルートを明確にしている医療従事者ほど、不安が少ないという調査もあります 。
訓練後、家族に「避難したらこうする」と共有すると、家族側の理解が深まるだけでなく、
自身の行動開始の心理的安心にもつながるという調査があります。
5️⃣訓練体験を職場に還元できる自分を発見
- 訓練で気づいたことをすぐ提案すると、多くの同僚が「それ、気づかなかった!」と反応。
- 私も「ここに非常用ライト置いたらもっと効くよね」と提案→実際に設置されたことで、
ママナースとしての“行動力”=価値に変わりました。
訓練で気づきを提案することで、
「ナースの視点が職場を変える力になる」と実感できるようになりました。
これは個人の成長と組織の改善に直結する瞬間です。
✅見出し⑥|実際に参加したママナース3人の“訓練活用法”
👩⚕️Case A:乳児と一緒に訓練見学して安心UP!
「子どもに“ママすごい!”って言われたのが嬉しくて。家庭でも訓練の話題にできて安心感に変わりました」
「訓練に子どもと一緒に参加して、“ママ本当にすごい!”と言われ、自尊心UP。家でも災害時の話が自然にできるように」
👩⚕️Case B:夫と一緒に“家庭内避難訓練”で役割共有
「訓練後“うちはオムツ担当ね!”と夫と役割を決めたら、いざという時の見通しが立って、二人とも心が安定しました」
「訓練後、夫と非常バッグをチェックし合う時間を作ったら、お互いどこに何があるかパッと分かるようになりました」
👩⚕️Case C:VR導入訓練にチャレンジして“リアル避難”が体感できた
「訓練だけでは気づけない“恐怖と焦り”がVRで体感できた!子どもにも“部屋を○時に出る練習”をし始めました」
「VRの火災体験で、視界が制限され焦る感覚を事前に体感。部屋で子どもと『ここで止まらない練習』を始めました」
🔗見出し⑦|さらに読みたい人へ:記事リンク&収益への自然導線
🔍おすすめの関連記事
- 🧰 防災グッズを実際に使ってレビューしたい方へ
👉 【看護師 防災グッズ 実体験】職場&家庭で使える15アイテム - 🏃♀️ 避難の実際の段取りを学びたい方へ
👉 【看護師 避難 行動】災害時“何をどう持ってどう動く?”行動マニュアル - 🍽️ 家族の食事備蓄を知りたい方へ
👉 【看護師 ローリングストック】日常備蓄のコツと実践法
見出し⑧📝まとめ|“本当に動ける備え”は、訓練でしか身につかない
防災訓練は、忙しい看護師にとって「また予定が増える…」と思いがちなものかもしれません。
でも実際に参加してみると、それは机上のマニュアルでは得られない、生きた知識と体感の宝庫です。
- 「誰に何を伝えるのか」
- 「どの道をどう避難するのか」
- 「何を持ち出し、誰が先導するのか」
こういった“当たり前だけど緊急時には忘れがちな行動”を、
実際に動いて覚えることができるのが訓練の一番の価値だと思います。
ママナースとして家庭を守りつつ、医療従事者として職場を支える私たちだからこそ、
「想像で終わらせない、防災力」を育てていきたいですね。
「防災グッズも気になる!という方へ——」
👉 【看護師 防災グッズ】ママナースが実際に選んだ“本当に使える”15アイテムはこちら
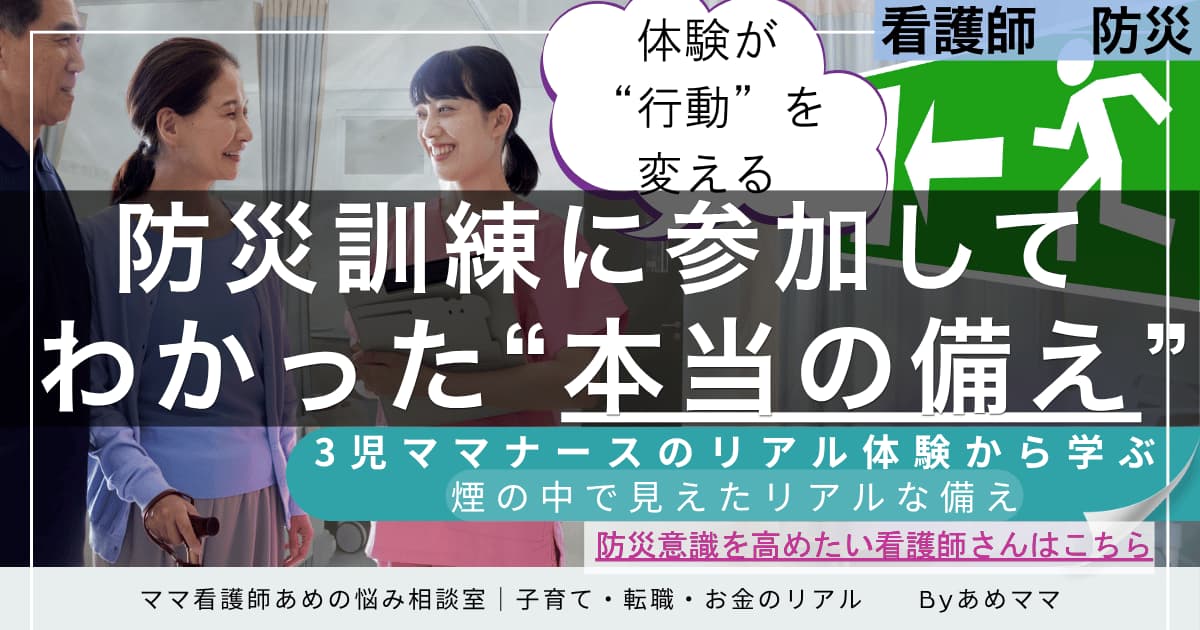
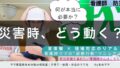

コメント