「この人に、もっと寄り添いたかった──」
新卒のころ、初めて看取りを経験したときのことです。
私は患者さんの死を受け止めるのに精一杯で、
残されたご家族にどんな言葉をかけていいのかもわからず、
ただ事務的に手続きをこなすことしかできませんでした。
それがずっと、心のどこかに残っていました。
そして今。転職して働く病院では、終末期の患者さんと関わる機会が多くなり、
「この人は人生の最期に、どんな時間を過ごしたいのかな」
「私はその人に何ができるだろう」──
そんなことを真剣に考えるようになりました。
そのとき出会ったのが「終末期ケア専門士」という資格です。
今、私はこの資格の取得を本気で考えています。
この記事では、私が感じてきた迷いや気づきを交えながら、
同じように悩んでいる方へ、この資格がどう役立つかをお伝えできたらと思います。
終末期ケア専門士とは?
「終末期ケア専門士」は、日本終末期ケア協会が認定する民間資格で、
終末期にある患者さんとご家族を、より専門的かつ包括的に支援する力を養うことを目的としています。
対象は、看護師・介護士・ケアマネージャーなど医療や福祉の現場で働く人たち。
一定の実務経験を持つことが受験の条件となっており、
知識だけでなく実践力のある人材を目指す資格です。
「終末期ケア」と聞くと、“看取り”の場面を思い浮かべるかもしれません。
でも実際には、身体的なケアだけでなく、心理的な支援、ご家族との関わり、
さらには本人の尊厳や希望をどこまで大切にできるかが問われます。
私がこの資格を知ったとき、「こういう学びが必要だった」と、素直に思いました。
“あのとき”の自分に戻ることはできないけれど、
これから関わる患者さんやご家族のために、もっとできることがあるかもしれない。
そんな気持ちで、この資格の取得を目指しています。
受験資格と試験概要
「資格って、取りたいと思っても条件が厳しそう…」
そう思っていた私でも、終末期ケア専門士の受験資格を調べたとき、
「これなら目指せるかも」と前向きになれました。
終末期ケア専門士の受験には、一定の実務経験が必要です。
具体的には、看護師・介護士・介護支援専門員(ケアマネ)・医師・薬剤師・管理栄養士など、
医療福祉分野の国家資格を持ち、実務経験が3年以上ある方が対象となります。
私自身、看護師としての実務年数が要件を満たしていたため、
「勉強を始めれば挑戦できる」と現実的な目標として捉えることができました。
試験は、毎年1回(主に秋頃)に実施されます。
内容はマークシート形式の選択問題が中心で、
公式テキストやWEB講習会を通じてしっかり準備していれば、合格は十分狙えます。
出題範囲には以下のようなテーマが含まれています:
- 終末期ケアの基礎知識
- 医療・看護・介護におけるチームアプローチ
- 倫理・尊厳の保持
- ご家族や関係者との関わり方
- 実際の支援場面での判断と対応 など
特別な論文提出や面接はないため、実務経験を活かしつつ、
計画的に学習を進めていける方にはおすすめの資格です。
「難しそう…」という不安を手放して、
「今の自分でも目指せるんだ」と感じてもらえる資格だと思います。
学習方法と勉強のコツ
終末期ケア専門士を目指すにあたって、まず気になったのは「どうやって勉強すればいいんだろう?」という点でした。
私が最初に取り組んだのは、協会が出している公式テキストです。
このテキストは、試験範囲の知識を網羅的にカバーしていて、
基礎から順を追って学べるように構成されています。
内容は専門的ではありますが、図表や事例も多く、
「現場でこういうこと、あるある…」と共感しながら読み進めることができました。
ただ、独学だけだと理解に不安が残るところも正直あって、
そんなときに見つけたのが、WEB講習会という選択肢です。
これは公式が提供しているオンライン講義で、
テキストの内容を補完しながら、講師の解説を動画で受けられるスタイル。
自宅でスマホやPCから視聴できるので、夜勤の合間や子どもが寝たあとでも学習できたのがありがたかったです。
私は「最初はテキストで全体像をつかんで、苦手な分野はWEB講習会で理解を深める」
という形で進めています。自分のペースで学べるので、忙しい看護師やママナースにも向いていると思います。
何より、“ただ試験に受かるための勉強”ではなく、
「この知識、明日からのケアにも活かせるな」と実感できるのが大きな魅力です。
資格取得のメリット
終末期ケア専門士を目指して勉強を始めてから、私自身、日々のケアの見方が少しずつ変わってきたのを感じています。
「この患者さんは今、何を望んでいるんだろう」
「ご家族が言葉にできない気持ちを、どう受け止めたらいいだろう」
以前よりも、“今ここ”の声に丁寧に耳を傾けるようになった気がします。
資格を持っている=すごい、ということではありません。
でも、終末期ケアについてしっかり学んだという事実が、
自分に少しずつ自信や視野の広がりをもたらしてくれているのは確かです。
また、キャリア面でもメリットはあります。
- 緩和ケア病棟や在宅医療チームでのアピールポイントになる
- 看取りケアに力を入れている施設への転職にも有利
- 認知度は徐々に高まりつつあり、履歴書に記載することで印象が残る
そして何より、資格取得のプロセス自体が
「自分はどういう看護がしたいのか?」を問い直す、貴重な時間になります。
終末期ケアに関心がある方にとって、
この資格は単なるスキルアップだけでなく、“心の軸”をつくる学びになると思います。ます。
資格取得後の活躍の場
終末期ケア専門士の資格を活かせる場は、思っているよりも広がっています。
私の職場のように、終末期の患者さんが多い療養病棟や高齢者施設はもちろん、
以下のような場所でもニーズが高まっているのを感じます。
- 緩和ケア病棟(がん末期の疼痛緩和や心の支援を行う)
- 在宅医療チーム(自宅で最期を迎える支援)
- 介護施設(看取りの方針が導入されるケースが増加)
- 訪問看護ステーション(地域包括ケアの中核として活躍)
また、医療職だけでなく、介護職・福祉職の方でも資格取得者が増えているとのこと。
チームで支える終末期ケアにおいて、“共通言語”としてこの資格が役立つ場面も多くなっているようです。
さらに、現場だけでなく、教育・啓発活動の分野でも活躍している人がいます。
- 終末期ケアについての勉強会や地域イベントでの講師
- 施設内の職員研修やリーダー役
- 看取り体制の整備に関わる役職へのステップアップ
「資格を取ったから、すぐに何かが変わる」というわけではありません。
でも、ケアの質を高めたいという意志を、かたちに残せる。
それが、この資格の持つ価値のひとつだと私は感じています。
費用と更新制度
資格を取ろうとするとき、やっぱり気になるのが費用ですよね。
私も「何万円もかかるのかな…」と心配でしたが、調べてみると終末期ケア専門士の取得費用は比較的現実的なものでした。
まず、必要な費用の目安は以下の通りです:
- 受験料:11,000円(税込)
- 公式テキスト代:3,300円(税込)
- WEB講習会受講料:11,000円(税込)
合計しても、約25,000円程度。
国家資格の受験や専門講座に比べると、自己投資としては手が届きやすい水準だと感じました。
また、公式テキストとWEB講習会は必須ではなく、自分に合った学習スタイルで選べるのも嬉しいポイントです。
資格取得後の更新制度についても、そこまで負担は大きくありません。
- 有効期間は5年間
- 更新には「継続学習」や「実務経験の記録」などを提出し、指定単位を満たすことで更新可能
毎年更新が必要な資格と比べて、更新頻度が少なく、実務に活かしながら長く維持できる資格だといえます。
私自身、「これならムリなく続けられそう」と感じられたことが、
資格取得を前向きに考えられた理由のひとつでもあります。
私が“終末期ケア専門士”を目指す理由と、あなたへのメッセージ
終末期ケア専門士という資格を知って、
「これは今の自分に必要な学びかもしれない」と、私は素直にそう思いました。
新卒の頃にできなかったこと、寄り添えなかった想い。
それは今も時々、私の中に小さく残っています。
でもだからこそ、これから関わる患者さんやご家族には、
できる限り“あたたかい時間”を届けたいと心から思うようになりました。
この資格を取ったから劇的に何かが変わるわけではないかもしれません。
でも、「ケアに向き合う姿勢」や「自分を信じる気持ち」が、少しずつ変わっていく気がします。
もし今、終末期ケアに向き合う中で
「もっと自分にできることがある気がする」
「でも、どうしたらいいか分からない」
そんな気持ちを抱えているなら、
この資格を“学びの入り口”としてのぞいてみてほしいなと思います。
🔍 「終末期ケア専門士」以外にも、今の自分に合う資格を探したい方へ
👉 看護師のスキルアップ資格まとめ記事はこちら
📘 まずはテキストで全体像をつかみたい方はこちら
👉 [終末期ケア専門士公式テキストをチェックする]
🎥 自宅でじっくり学びたい方にはWEB講習会もおすすめです
👉 [終末期ケア専門士WEB講習会を見る]
あなたの学びが、これから出会う誰かの“最期の時間”を、少しでもやさしいものにできますように。
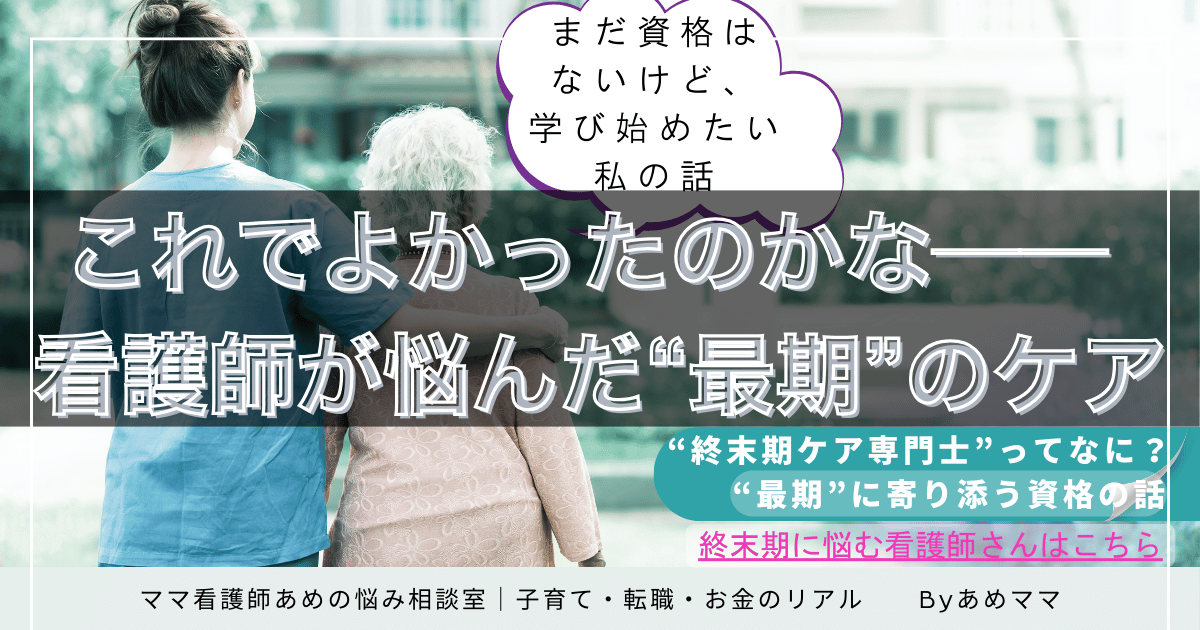
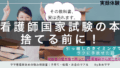
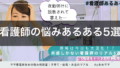
コメント